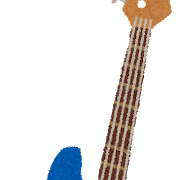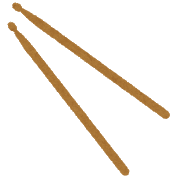ギターは生演奏で録音する人が結構いますが、ベースはソフト音源を使って打ち込みにしてる人が多い印象があります。
とはいえ、ベーシストであるなら自分で弾いたものを録音して使いたい、そう思っている人もいることでしょう。
そこで今回は、ベースの宅録で必要な機材について解説していこうと思います。
DIを使って直の音を録る
ギターの場合ハードかプラグインかの2択があり、音の調節の可否やレイテンシーによって自分の持っている環境と相談して決めることになりますが、ベースの場合はDIから直の音を録ることが鉄則となっています。
なのでDIは必須といいたいところですが、最悪なくても録音はできます。が、DIを使うことでノイズ対策になり安定した信号で録音できるようになります。
つまり、クリアになる!
だからDIはなくても録音自体はできるけれど、音質のためにもDIは必須レベルで必要なものになります。
そしてもう一つ、どうしてベース直の音じゃないといけないのか、ということについても触れておきます。
レコーディングで先にアンプやエフェクターを使ってしまうと、ベースの音色そのものがオケに馴染まないなんてことがおこる可能性があります。
基本は後がけです。ようするにプラグインを使いましょう、アンプシミュレーターを使いましょう、そういうわけです。ギターもできるならプラグインを使うことをおススメしますが、ベースとは違ってハードでも問題ない場合が多いので(音色そのものが歪み等使っている)、その点はベースと違うところになりますね。
ミキサーがあると便利
先ほどもいったようにベースはアンプやエフェクターは後がけが鉄則です。
でも自分で音を作ってそれを聞きながら録音しないとうまく演奏できなかったり、気分が乗らなかったりなど、やっぱり音色を変えて録音したいものですよね。
そこであると便利なのがミキサーになります。
ミキサーは音量の調整をするだけのものではなく、機種によってインプット・アウトプット数がいくつもあります。つまりインプットに応じて入力でき、アウトプット数に応じて出力できます。さらに各チャンネルの音量を調整できるので聞きたい音だけを聞いたり消したりといった調整が可能になります。
そのミキサーを使うことで音色を変えても問題ない環境を作ることができます。
接続順は以下になります。
- ベースからDIへ接続
- DIからオーディオインターフェイスに接続
- オーディオインターフェイスからパソコンに接続
- DIからエフェクターに接続
- エフェクターからミキサーに接続
- ミキサーにヘッドフォン接続
DIからの出力が2つありますね(2と4)。出力端子が2種類あるので分岐して使うことができます。それを利用してパソコンにはDIを使った直の音、ヘッドフォンではエフェクターを通した音をモニターしながら録音できるというわけです。もちろん、オーディオインターフェイスとミキサーを接続することでパソコンに入ったDI直の音を聞くこともできます。ミキサーを使うことで可能となる接続方法です。
レコーディングスタジオでベースを録る場合に採用される接続方法になりますね。
とはいえ今回はあくまでも宅録の話。こんなにがっつりとやらなくてもいいというのであれば、
ベース➡エフェクター(アンプ)➡DI➡オーディオインターフェイス➡パソコン
でもいいと思います。音に納得がいってるのならなおのことこれでいいのかなとは思います。
僕が言いたいところはベースの音色がオケに馴染まないときに困るというだけなので、これでオケに馴染めば問題なしです。
ただし何度も言うように、一度エフェクターを通して録った音色をクリーンに戻すことはできません。後がけだからこそ編集ができて、ミックスでオケに馴染ませる編集作業がしやすくなります。その点を踏まえて、できることならばDIから直の音でレコーディングした方がいいと思います。
ライン録りで十分
そもそも宅録でマイク録りは環境を用意するのが厳しいと思います。
それに最近のアンプシミュレーターの性能はとても高いのでライン録りでも十分いい音で録れます。
レコーディングスタジオとなれば話は別ですが、宅録の場合はパソコンとDIとアンプシミュレーターとオーディオインターフェイス、この4つがあればベース録りは可能です。
まとめ
今回はベースの宅録について解説してきました。
正直僕は打ち込みで済ませているのですが、僕のように打ち込みで済ませている人は少なくないと思います。それほどベース音源のクオリティは高いです。
ですがベーシストであれば自分の音で録りたいでしょうし、やはり生演奏のほうが細かいニュアンスは出せますし生演奏ならではの迫力やうま味はあります。その点は間違いなく打ち込みの限界を突破する部分だと思いますし、今回の解説が生演奏で録りたいと思っている人への助けになれれば幸いです。
それでは最後までお読みいただきありがとうございました。